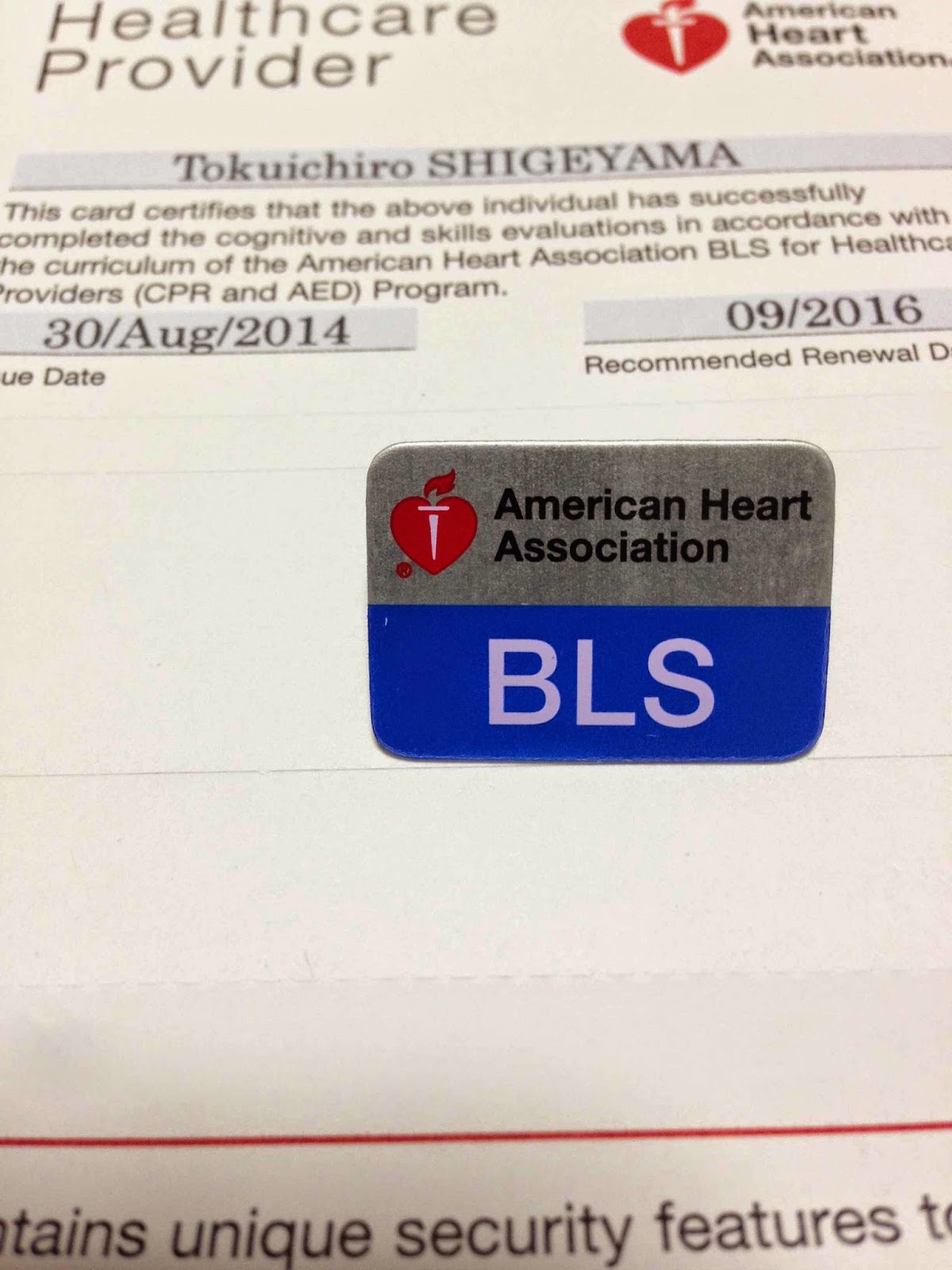かねてより、
第7回徳讃会は演目の解説がありませんという旨、お伝えしていたかと思うのですが、その代わり、こちらのブログで、ごく簡単に(僕の理解した範囲で)解説を試みておこうかと思います。※多少ネタバレ?はあるかも知れません。悪しからず^^;
さて、
初番の狂言「以呂波」に出てくる「いろは」ですが…。Wikipediaの記述を引用しますと、“いろは歌(いろはうた)とは、すべての仮名を重複させずに使って作られた誦文のこと。七五調の今様の形式となっている。のちに手習いの手本として広く受容され、近代にいたるまで用いられた。また、その仮名の配列は「いろは順」として中世から近世の辞書類や番号付け等に広く利用された。ここから「いろは」は初歩の初歩として、あるいは仮名を重複させないもの、すなわち仮名尽しの代名詞としての意味も持つ。”
いろはにほへと ちりぬるを 色は匂えど 散りぬるを
わかよたれそ つねならむ 我が世誰そ 常ならむ
うゐのおくやま けふこえて 有為の奥山 今日越えて
あさきゆめみし ゑひもせす 浅き夢見し 酔ひもせず
京
大まかにまとめると、すべてのひらがなを重複しないように使って、詠んだ歌ということになります。
「京」というのは拗音(ちっちゃな「ゃ」「ゅ」「ょ」のこと)を習わせるために付け加えたとか……(へぇぇぇ!そうなんや(゜o゜;)
で。
「作者は誰なんか!?」ってハナシですが。狂言「以呂波」の中では、「高野の弘法大師の作らせられた、四十八文字の『いろは』というがある…」と述べていますが、現代の学説では確証はないようです(どちらかと言えば否定的?)
写真は、京都の東寺へ参った折(骨董市)に、息子殿に見せたろと思って撮影してきた分です。
→弘法大師(空海)
一説には、弘法大師とは異なる別の作者が、遺恨を詠み込んだ「暗号説」という話もあり、「咎無くて、死す」という文言を読めるとかΣ(゜д゜
さてさて。
狂言「以呂波」は、親が子どもに「手習い」(読み書き)を教えるのに難渋するというお話(これまたザックリとしたまとめだナ…^^; )なのですが、そのなかでも当時の風習を知らないと少し分からないかも。という事柄に少し触れておきたいと思います。途中、親と子の対話が「連想ゲーム」のような様相になってくるわけですが、「藺(い)を引けば灯心が出まする。」という言葉があります。
「いろは」の「い」に連想して「藺」について、子が述べるわけです。
これは、古くは「藺:い草」の髄を灯明油に浸して照明にした事によります。
☞い草の栽培は、こちらのブログ(奈良県安堵町の伝統産業 灯芯引き)を御参照下さい。
☞灯明の点灯に際しては、こちらのお店の販売サイト(油でともす和の灯り、臭いもなくモダンです)を参考にしました。
我が師に尋ねると、
「灯明油は仏具屋にあるんとちゃうか?」とのことで、職場近くの仏具屋さん、地元の仏具屋さんをハシゴしてみましたけれども、1軒は業務用の一斗缶での販売のみ、もう1軒は取り扱いなし。さらにもう1軒は「ウチでは取り扱ってないけど、菜種油を探さはったらヨロシで?」とのこと……。(せやかて、スーパーで、普通に菜種油なんか売ってへんがな^^; )
4軒目も回ったのですが、そこは既にお店畳んではりました(…ので、ここで力尽き、Amazon大先生にお伺いする事にしました。)
ははぁ…。
さすがは、Amazonには何でもあります。しかし、灯明油は何だか割高なんですよね^^;
そこで、ふと思い出しました。「灯明油は、菜種油や!」って話。
じゃ、この際、菜種油の風味にも個人的には興味があるし、菜種油買うとこかい!ってことで、食用菜種油をAmazonで買い求めました。
亡祖父、
玄三郎の遺品を整理した折に、「あ。灯心あるわ。これ、『以呂波』の解説に使えるな。」という事は、前から思っていたのです。ですので、Amazonで買い求めたのは、菜種油のみになります。(なんと、灯心も売ってましたけども!)
また、右下の丸いのが、「灯明皿」と呼ばれるものでしょう。その下には「受け皿」があって、2重になってます。皿の中央に乗っているのは「掻き立て」と呼ばれるものですね。
以前に確認したときは、箱の中身を精査しなかったのですが、祖父の記した覚書が入っていました。
先達が用いた、いにしえの照明器具の参考として、また以呂波の参考品として、後世に伝えるために、灯心などを探し求めた旨、書かれています。
…ありがとう、爺さま。こうしてブログになりました。
はい。そしてこれが灯心です。
祖父は、3束買い求めてたみたいですが、1束は既に封切られていました。
触るとふわふわした感じがします。
実際に菜種油に浸して(割とすぐに浸透します)着火するわけですが、上記の引用したお店の内容に従い、3本に火を付けました。
明るさは文字が何とか読める感じでしょうか。
燃焼中は、臭いもさほど気になりませんでしたが、消火後、少し別室に外して戻ってきたところ、割と臭いが気になったので、やはり最終的には換気扇を回しました。(煙もあまり出ない印象ですが、油の質によるのでしょうか?)
燃焼時間。
おおよそ、30分というところでしょうか。個人的な印象としては、割とすぐに油がなくなるなぁ……という感じです。この調子だと、大きな灯明皿にでもしない限りは、すぐに継ぎ足していかなければならないような気がします。そして、菜種油のお味。
卵焼きを作ってみました。独特の風味があるのですが、これは好みが分かれるところかも知れません。(僕はわりと好きです。)ただ、オリーブオイルのような洋風なイメージを持ってると、思いっきりガクッとくるかも知れません。和風の炒飯とかに良さそうです。(和風炒飯は祖母に教わった料理です。)
さて。次に「ろ」。
「ふねにはろかいがいりまする。」と、「いろは」の「ろ」に反応して子は言いますが、これは「船には艫と櫂が要ります!」と言っています。
しかし、適当な写真がありませんし、身近で撮影に行けそうなところも思い当たりませんので、こちらのサイト(艪櫂用語)を参考にしました(第2項と4項が該当するかと思います。)
そして。「ちり」。
「ちりぬるをわか」の「ちり」ですが、これと「塵」を掛けるわけですね。「ろ」から「はにほへと」が飛んでしまっていますが、あんまり余計な事を子が言うので、親もちょっとイラッ!として忘れたのかも知れませんね^^;
いずれにしても、猪口才な子どもである事は確かです(実はリアルでもそうです(-。-;) )
最後は……。
現代ではちょっとアレな内容?なのかも知れませんが、今も昔も子育てには苦労したんだなぁ…(-。-;) という事が、身につまされてよく解るのです(ええ。ごく個人的にですが。)ま。そんなわけで。
息子殿にはきっとはまり役なんだろう。と思うのですが……(笑)
第7回「狂言を楽しむ 徳讃会」のチケットは、明日10月1日からお申し込み受け付け開始です。全席60席(お申し込み順)となっています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。